Library 発達障害支援に関する研究・調査
-
はじめに
近年、発達障がいのある方は増加傾向にあると指摘されています。文部科学省が令和4年に公表した調査では、公立小中学校の通常学級に在籍する児童生徒の8.8%に発達障がいの傾向があると報告されました。また「大人の発達障害」という概念の認知も広がり、新たな社会的課題として認識されつつあります。
しかし、その一方で、この分野は未だ研究途上にあるため、支援の現場における実態を示すエビデンスや定量的なデータが不足していることも事実です。
こうした状況を踏まえ、当協会は、発達支援の現場における実態を可視化し、実践的な知見を集積することを目的とした専門チームを発足いたしました。本ページでは、当事者やそのご家族、支援者の皆様から直接お寄せいただいた貴重な声(一次情報)を、プライバシーに配慮した上で掲載するとともに、それらを分析・統計処理したデータ(二次情報)も随時公開してまいります。これらの情報は、論文や書籍、各種メディアでの引用も可能です。ご利用の際は、本ページ最下部に記載の「引用に関するガイドライン」をご確認ください。
本取り組みが、発達障がいへの理解を深め、より良い支援環境を構築する一助となることを心より願っております。 -
調査報告①(2025年9月1日発行)
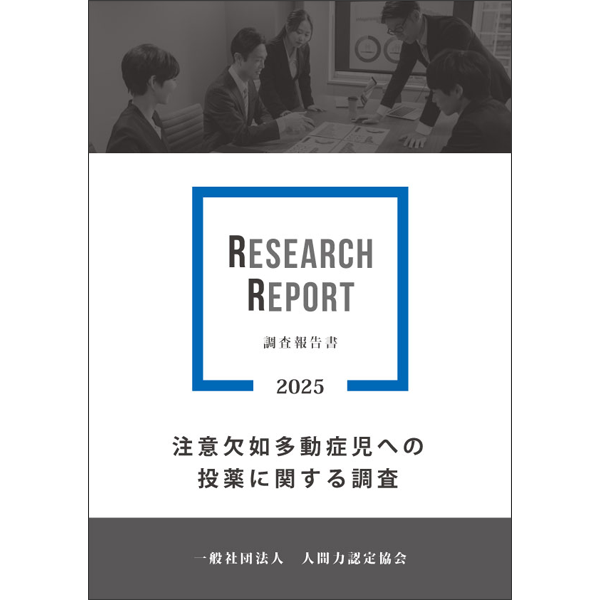 【本調査の要約】
【本調査の要約】
本報告書は、注意欠如多動症(ADHD)児への投薬に関する保護者54名の実態を調査したものです。調査から、保護者が副作用への不安と子どもの困難を和らげたい希望の間で深く葛藤している現実が明らかになりました。約9割が何らかの改善を実感する一方、約8割が食欲不振等の副作用があったと回答しており、投薬の「光と影」が示されています。本調査は、投薬をするか否かは非常に難しい選択であり、客観的情報や薬だけに頼らない支援の重要性を示唆しています。 -
調査報告②(2025年10月1日発行)
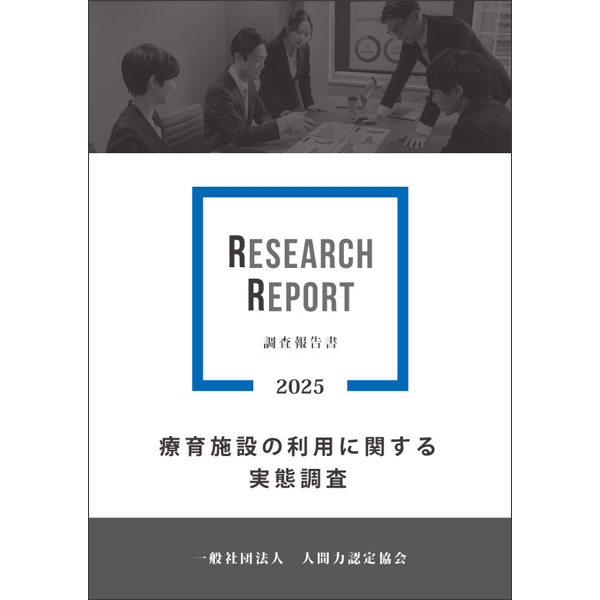 【本調査の要約】
【本調査の要約】
本報告書は、療育施設を利用する保護者126名の調査結果です。施設選びでは専門プログラム以上にスタッフとの信頼関係が重視され、療育が子どもの発達を促すだけでなく、孤立しがちな保護者の精神的支えという重要な役割を担う実態が明らかになりました。子どもの療育施設適応は良好なケースが多く、家庭と施設の密なコミュニケーションが成功の鍵であることも浮き彫りになりました。 -
調査報告③(2025年11月1日発行)
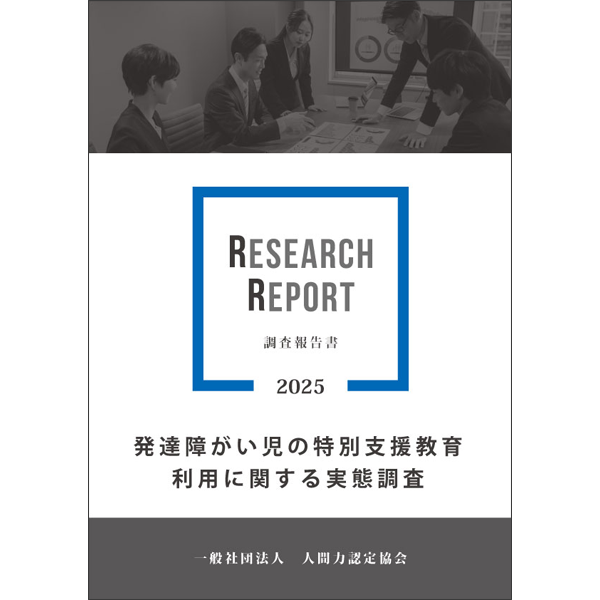 【本調査の要約】
【本調査の要約】
本報告書は、特別支援教育を利用する保護者63名の調査結果です。保護者は葛藤の末、「子どもの安心」を最優先に特別支援教育の利用を決断している実態が明らかになりました。特別支援教育を利用して最も良かった点は「心理・情緒の安定」であり、手厚い支援が子どもの「居場所」と「自信」の獲得に繋がっています。本調査は、特別支援教育が選択可能な学びの場の一つであることを示しています。 -
調査報告④(2025年12月1日発行)
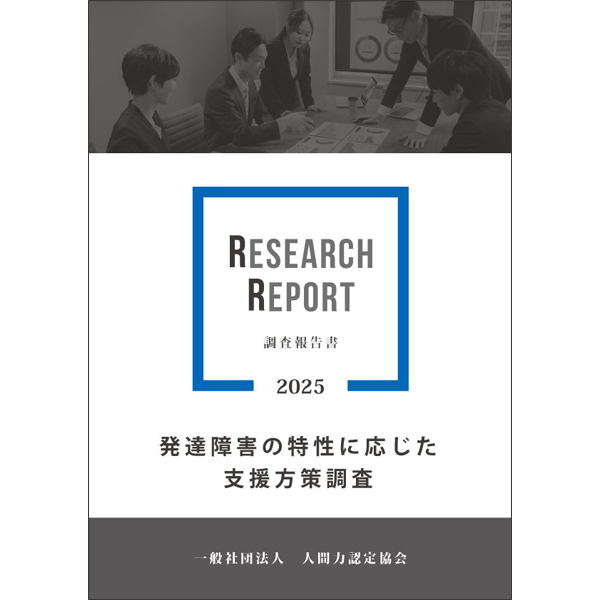 【本調査の要約】
【本調査の要約】
本報告書は、発達障害の特性に応じた具体的な支援方策を明らかにしました。癇癪や忘れ物などの困りごとに対し、支援の核となるのは「子どもの内面への共感と受容」であることが示されました。また、絵カードやリスト等の視覚的ツールを用いた環境調整により、子どもが見通しを持って主体的に行動できる「わかる・できる環境」を整える工夫が有効であるとわかりました。唯一の正解はなく、多様な支援策を組み合わせる重要性を示唆しています。 -
研究チームの活動実績
1.実態調査の実施(一次情報の収集)
・療育施設利用に関するエピソード
・「困った」を乗り越えた成功エピソード
・特別支援教育に関するエピソード
・ADHD児の投薬に関するエピソード
・カサンドラ症候群に関するエピソード
・子どもの二次障害に関するエピソード
・子どもに発達障害であることをどう伝えたか?
・小学校~大学の受験時に関する困った経験談
・アンガーマネジメントに関するエピソード
・感覚過敏/鈍麻に関するエピソード
2.調査報告書を教育委員会に提供
3.調査報告書を全国225校の大学、短期大学に提供
・幼稚園教諭免許状または保育士資格が取得可能な大学および短期大学へ調査報告書を提供
4.調査報告書を全国132校の専門学校に提供
・幼稚園教諭免許状または保育士資格が取得可能な専門学校へ調査報告書を提供
5.調査報告書を全国8,000を超える療育施設に提供
【引用に関するガイドライン】
当サイトに掲載されているコンテンツ(記事、調査データ、エピソード、画像、動画等)の著作権は、一般社団法人 人間力認定協会または正当な権利を有する第三者に帰属します。
当サイトのコンテンツは、以下に定めるルールを遵守いただく場合に限り、無償で「引用」いただくことが可能です。
1.引用の基本ルール
以下のすべての条件を満たす場合に、「引用」として無償での利用を許可します。
【出典の明記】
引用箇所に、出典元が一般社団法人 人間力認定協会であることを明確に記載してください。
【引用元へのリンク】
ウェブサイトやSNSなどで引用する場合、出典の記載箇所から、引用元の記事(https://...)に対して、必ずリンクを設定してください。
【主従関係の明確化】
あなたが作成するコンテンツが「主」、引用部分が「従」となるようにしてください。引用部分がコンテンツの大部分を占めるような利用は「転載」とみなし、原則として許可しておりません。
【改変の禁止】
引用部分は、文章の趣旨を変えるような改変や、部分的な切り取り(恣意的な編集)を行わないでください。
2.禁止事項
以下のような利用は、固くお断りいたします。
・コンテンツの全文または大部分をコピーして利用する「転載」
・当協会の許諾を得ない、商用目的での利用
・画像やイラストのみを抜き出して利用すること
・当協会の社会的信用や品位を損なうような態様での利用
・違法なコンテンツや公序良俗に反するサイトでの利用
3.転載や二次利用をご希望の場合
書籍への掲載、テレビ番組での利用、セミナー資料での広範囲な利用など、「引用」の範囲を超える「転載」や二次利用をご希望の場合は、目的や利用媒体などを明記の上、下記のお問い合わせフォームより事前にご相談ください。
▼お問い合わせフォーム
https://ninkyou.jp/contact/
4.免責事項
当サイトのコンテンツを利用したことによって何らかの損害が発生した場合でも、当協会は一切の責任を負いかねます。また、当サイトの情報は、予告なく変更または削除されることがありますので、あらかじめご了承ください。
