第34回 児童発達支援士 意見交換会の実施報告
3-意見交換会
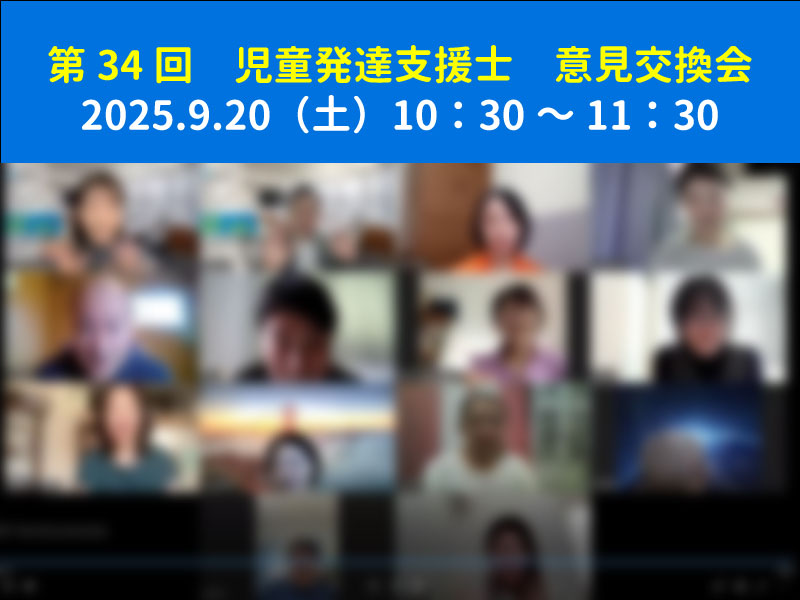
2025年9月20日に開催されたオンライン意見交換会では、子育て中の保護者の皆様と、教育・療育現場で活躍する専門家の方々が一堂に会し、活発な質疑応答が行われました。本記事では、その中から特に注目度の高かったテーマをピックアップし、当日のやり取りを簡単に要約した形でお届けします。
支援員と当事者の保護者の両方の立場を経験して感じたことは?
支援員としては、保護者の方に「支援級の方が手厚いですよ」とアドバイスすることがありました。しかし、いざ自分の息子が小学校でトラブルを起こし、学校から支援級を勧められた時は、「あれだけ早期介入して、色々な支援をしてきたのにダメだったのか…」と、とても辛く感じました。
ただ、最終的には息子本人が支援級を「すごく楽しい!」と気に入って通ってくれているので、今は気持ちがすっきりしています。
この経験を通して、支援者として関わるのと、自分の子のこととして当事者になるのとでは、受け止め方が全く違うということを身をもって実感しました。
ADHDのお子さんを育てる中で、特に幼少期に苦労したことは?
息子が幼かった頃は、今ほど社会に発達障害への理解がなく、専門の病院に行ってもなかなかうまくいきませんでした。
一番苦労したのは二次障害です。中学校の先生が息子の特性に理解を示し、特別に配慮してくださったのですが、それが息子にとっては「自分は特別だから、みんなと同じことをしなくてもいいんだ」という免罪符のようになってしまいました。その考えを修正するのが本当に大変でした。
今も29歳になりますが、失敗するのが怖くて新しいことに挑戦できないなど、引きこもりのような状態が続いています。
児童発達支援士の資格で学んだ手法(SSTなど)を実践した経験はありますか?
私はSST(ソーシャルスキルトレーニング)スペシャリストの資格を持っており、子どもたちに話し方を教える仕事で、資格で学んだトレーニング内容を取り入れています。これは障害の有無にかかわらず、多くの子どもにとって有効だと感じています。
普段のやり取りの全てにSSTの要素を取り入れることを意識しています。例えば、私が関わっている就労支援B型の利用者さんとのコミュニケーションでは、「こういうことを言ったら相手はどう思うかな?」と一緒に考えるような関わり方を心がけています。
うちの息子は口頭での指示が入りにくいため、「To-Doリスト」を使った視覚的な支援を実践しています。
具体的には、ホワイトボードに「連絡帳」「水筒」「宿題」といった学校の準備物をマグネットで貼り出し、準備ができたら「できた」の欄に移動させる、というものです。これを使うようになってから、本人がどこまで準備したかを自分で確認できるようになり、自信にも繋がっているようです。学校の先生にもお願いして、教室でも同じものを使ってもらっています。
ご自身のADHDについて。子ども時代に「こうしてほしかった」「こう言ってほしくなかった」ことは?
私がADHDの診断を受けたのは4年ほど前です。
子ども時代を振り返って「こう言ってほしくなかった」と感じる言葉は、「〇〇ちゃんはできるのに」という、他人との比較の言葉です。これは大人になるまでずっと、呪いのように心に引っかかっていました。
逆に「こうしてほしかった」ことは、もっと積極的に会話をして、私のことを認めてほしかったということです。私の両親は忙しく、日常の何気ない会話をする機会が少なかったため、私は自分の気持ちをうまく表現するのが苦手になってしまいました。日々のコミュニケーションがとても大切だと思います。
【まとめ】第34回 児童発達支援士 意見交換会の実施報告
今回もご参加いただいた皆様ありがとうございました。
今回お話にあがった内容をもとにこれからも様々なサービスを展開していきたいと思います。
ご参加いただきました皆様ありがとうございました。
一覧に戻る