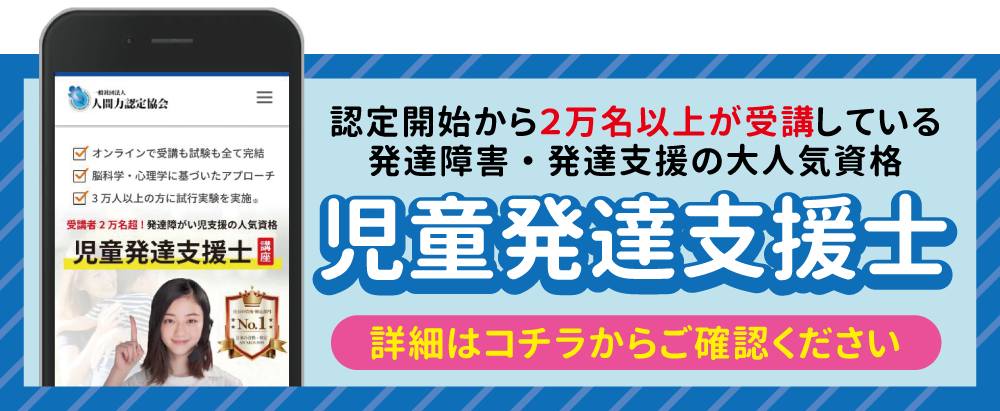【完全版】発達障害の種類を徹底解説|子どもの特性を理解し、未来を支えるためにできること
6-その他

「うちの子、ちょっと落ち着きがないかも…」
「周りの子と比べて、言葉が少し遅い気がする」
「特定のことにものすごくこだわるけど、これって個性?」
子育てをしていると、こうした疑問や不安を感じる瞬間は誰にでもあるかもしれません。近年、「発達障害」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その具体的な意味や種類、そしてどのように向き合っていけば良いのかを正確に理解している方は、まだ多くないのが現状です。
この記事では、「発達障害」とは何かという基本的な知識から、その代表的な種類である「自閉スペクトラム症(ASD)」「注意欠如多動症(ADHD)」「限局性学習症・学習障害(LD)」などを、具体的な例を交えながら詳しく解説します。
この記事を最後まで読むことで、あなたは以下のことを得られるはずです。
- ・発達障害の多様な種類とそれぞれの特性についての正しい知識
- ・「育て方が悪いのかも」という不安から解放され、子どもの特性を客観的に見る視点
- ・子どもたちが直面する困難を理解し、適切なサポート方法のヒント
- ・子どもの未来をより明るく照らすための、専門的な関わり方への道筋
子どもの個性を輝かせ、その可能性を最大限に引き出すための第一歩は、「知る」ことから始まります。ぜひ、最後までお付き合いください。
第1章:そもそも「発達障害」とは?
まず、最も大切なことからお伝えします。発達障害は、親の育て方やしつけが原因で起こるものでは決してありません。生まれつきの脳機能の発達の仕方の違いによるものであり、「病気」というよりは「特性」と捉えるのが適切です。
サッカーが得意な子、絵を描くのが好きな子がいるように、発達障害もその人の「個性」の一部です。
では、なぜ「障害」という言葉が使われるのでしょうか。それはその特性によって、本人が社会生活や学校生活を送る上で、さまざまな困難(生きづらさ)を感じることがあるためです。つまり、本人の特性と、周囲の環境との間にミスマッチが生じることで、「障害」として顕在化するのです。
大切なのは、発達障害は白か黒かで分けられるものではなく、誰もがその特性を少しずつ持っている「グラデーション(スペクトラム)」であるという視点です。診断名がつくかつかないかに関わらず、一人ひとりの特性の濃淡は異なります。この理解が、偏見なく向き合うための基礎となります。
>>ADHD・自閉症診断テスト|子ども発達障害チェックリスト【協会監修】
第2章:【種類別】発達障害の主な特性を徹底解説
ここからは発達障害の代表的な種類と、それぞれの特性について詳しく見ていきましょう。お子さんや周りの人を思い浮かべながら読んでみてください。
1. 自閉スペクトラム症(ASD)
かつては「自閉症」「アスペルガー症候群」などと別々に診断されていましたが、現在はそれらの特性が連続体(スペクトラム)上にあるという考えから、「自閉スペクトラム症(ASD)」という一つの診断名に統合されています。
ASDの主な特性は、大きく2つに分けられます。
① 対人関係やコミュニケーションの困難さ
【相手の気持ちを察するのが苦手】
「空気が読めない」と言われたり、冗談や皮肉が通じにくかったりします。「少し静かにしてね」と言われても、「少し」がどの程度なのか分からず、戸惑ってしまうことがあります。
【視線を合わせるのが苦手】
人と話すときに、目が合わない、あるいは合わせようとしないことがあります。これは悪意があるわけではなく、視線からの情報が多すぎて混乱してしまうためです。
【一方的な会話になりがち】
相手の反応を気にせず、自分の好きなこと(電車、恐竜、アニメなど)を一方的に話し続けてしまうことがあります。
【言葉の発達の遅れや独特な使い方】
言葉を話し始めるのが遅い、あるいは相手が言った言葉をそのまま繰り返す「オウム返し」が見られることがあります。抑揚のない話し方をするのも特徴の一つです。
② 限定された興味・こだわり、感覚の特性
【特定の物事への強い興味】
電車の時刻表をすべて暗記したり、特定のキャラクターの情報を細部まで集めたりと、興味の対象が非常に限定的で、かつ深掘りする傾向があります。
【決まった手順やルールへのこだわり】
毎朝同じ道順で登校する、物の配置が少しでも変わるとパニックになるなど、変化を極端に嫌い、同一性を保とうとします。予期せぬ予定変更は大きなストレスになります。
【感覚の過敏さ・鈍感さ】
・感覚過敏: 特定の音(掃除機の音、サイレン)、光(蛍光灯のちらつき)、匂い、味、肌触り(服のタグ)などを極端に嫌がることがあります。人混みが苦手なのも、多くの情報が一気に入ってくるためです。
・感覚鈍麻: 逆に、痛みや熱さ、寒さなどを感じにくいことがあります。怪我をしても平気な顔をしていることもあり、注意が必要です。
これらの特性は、本人の「わがまま」や「自分勝手」なのではなく、脳の特性によるものです。その背景を理解することが、サポートの第一歩となります。
>>発達障がい児の癇癪・パニック、どう対応する?~ASD(自閉スペクトラム症)の子どもたちの事例から学ぶ~
2. 注意欠如多動症(ADHD)
ADHDは、「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの特性を特徴とします。これらの特性の現れ方によって、いくつかのタイプに分けられます。
① 不注意優勢型
【集中力が続かない】
授業中や宿題中に、他のことに気を取られやすいです。窓の外を飛ぶ鳥や、些細な物音にすぐ意識が向いてしまいます。
【忘れ物・失くし物が多い】
水筒や宿題のプリント、上着などを頻繁に忘れたり、どこに置いたか分からなくなったりします。整理整頓も苦手です。
【話を聞いていないように見える】
人が話している最中に、ぼーっとしてしまい、内容が頭に入ってこないことがあります。悪気があるわけではなく、注意を維持するのが難しいのです。
【物事を順序立てて行うのが苦手】
夏休みの宿題など、長期的な計画を立てて実行するのが非常に困難です。
このタイプは多動性のように目立った行動がないため、「おとなしいけど、うっかり屋さん」と見過ごされがちです。
② 多動・衝動性優勢型
【じっとしていられない(多動性)】
授業中に席を立って歩き回る、椅子の上でモジモジ・ソワソワする、手足を常に動かしているなど、静かにしているのが困難です。
【順番を待てない(衝動性)】
列に並ぶのが苦手で割り込んでしまったり、ゲームの順番を待てずに手を出してしまったりします。
【質問が終わる前に答えてしまう(衝動性)】
相手の話を最後まで聞かずに、思いついたことをすぐに口にしてしまいます。
【危険な行動に走りやすい(衝動性)】
よく考えずに道路に飛び出したり、高いところに登ったりすることがあります。
このタイプは、幼少期に気づかれやすいのが特徴です。
③ 混合型
不注意と多動・衝動性の両方の特性を併せ持つタイプです。
ADHDの特性は、「やる気がない」「しつけができていない」と誤解されがちですが、本人は「ちゃんとしなきゃ」と思っていても、脳の機能(特に前頭前野の働き)によって行動をコントロールするのが難しい状態なのです。
3. 限局性学習症・学習障害(SLD・LD)
限局性学習症(旧表現:学習障害)は、全般的な知的発達に遅れはないにもかかわらず、「読む」「書く」「計算する」といった特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す状態を指します。
本人は一生懸命努力しているのに、なぜかできない。その結果、「怠けている」と誤解され、自信を失ってしまうケースが非常に多いのが特徴です。
① 読字障害(ディスレクシア)
- ・文字を一つひとつ拾い読みするため、文章を読むのに非常に時間がかかる。
- ・単語や行を飛ばして読んだり、勝手読みをしたりする。
- ・似た形の文字(例:「わ」と「ね」、「め」と「ぬ」)を混同する。
- ・文章を読んでも、内容を理解するのが難しい。
② 書字障害(ディスグラフィア)
- ・文字の形を整えて書くのが苦手(鏡文字を書く、マスからはみ出すなど)。
- ・黒板の文字をノートに書き写すのに、極端に時間がかかる。
- ・漢字など、複雑な文字を覚えるのが非常に困難。
- ・頭の中では文章が浮かんでいるのに、それを文字にするのが難しい。
③ 算数障害(ディスカリキュリア)
- ・数の大小や順序の理解が難しい。
- ・指を使わないと簡単な計算ができない。
- ・繰り上がりや繰り下がりの計算でつまずく。
- ・図形やグラフの理解、時計を読むこと、お金の計算などが苦手。
これらの困難は、本人の努力不足が原因ではありません。文字や数字を処理する脳の神経回路が、多数派の人とは異なる働き方をしているのです。
>>学習障害(LD)診断テスト|6歳・7歳・8歳向けチェックリスト【協会監修】
第3章:発達障害とどう向き合うか?サポートの基本
発達障害の特性を理解した上で、次に大切なのは「どう向き合い、サポートしていくか」です。
【正しい理解と受容】
まずは「怠け」や「わがまま」ではなく「特性」なのだと、本人と周りが正しく理解すること。これが全てのスタートです。
【環境調整】
本人に「努力しろ」と求めるだけでなく、周りの環境を調整することが非常に重要です。
・自閉スペクトラム症の子には… 視覚的な指示(絵カードやスケジュール表)を使う、静かで刺激の少ない場所を用意する。
・注意欠如多動症の子には… 一度に多くの指示をせず、短く具体的に伝える。集中できる時間を短く区切り、休憩を挟む。
・限局性学習症の子には… 音声教材やタブレットPCを活用する、読みやすいフォントを使う、計算機やマス目の大きなノートを用意する。
【早期発見と早期療育】
子どものうちから困難さに気づき、適切な支援(療育)につなげることで、本人の「できた!」という成功体験を増やし、自信を育てることができます。これは、自己肯定感の低下や不登校、うつ病といった二次障害を防ぐ上で極めて重要です。
第4章:子どもの未来を支える専門家へ – 「児童発達支援士」という選択
ここまで読んでくださったあなたは、発達障害に対する理解が大きく深まったことでしょう。もしかしたら、こんな風に感じているかもしれません。
「もっと専門的な知識があれば、あの子の力になれるのに…」
「子どもと関わる仕事をしているけれど、今の知識だけでは対応に限界を感じる」
「自分の子どものために、もっと効果的な関わり方を学びたい」
その想いは非常に尊いものです。そして、その想いを具体的な「スキル」と「自信」に変える道があります。それが「児童発達支援士」資格です。
>>児童発達支援士・発達障害コミュニケーションサポーター資格【徹底解説】
なぜ今、児童発達支援士が求められているのか?
近年、発達障害への認知は広まりましたが、実際に子ども一人ひとりの特性に合わせた適切なサポートを提供できる専門人材は、社会的にまだまだ不足しています。保育園、幼稚園、学校、放課後等デイサービスといった教育・福祉の現場では、専門知識を持った人材が強く求められています。
また、悩みを抱える保護者の方は、「誰に相談すればいいのか分からない」「我が子にどう接すればいいのか」という深い孤独の中にいることが少なくありません。
児童発達支援士は、まさにそうした現場のニーズや保護者の悩みに応えるための、発達支援のプロフェッショナルです。
児童発達支援士になることで得られるもの
児童発達支援士の資格取得を目指す過程で、あなたは以下のような専門的な知識とスキルを体系的に学ぶことができます。
【深い専門知識】
この記事で紹介した以上に、発達障害の各特性や脳科学に基づいた背景を深く学びます。
【具体的な支援スキル】
子どもの行動の背景を分析し、適切なアプローチを考える「応用行動分析(ABA)」の考え方や、パニックを起こした際の具体的な対応方法、ソーシャルスキルを育むトレーニングなど、すぐに実践できるスキルを習得します。
【保護者支援のノウハウ】
子どもの支援は、保護者との連携が不可欠です。保護者の気持ちに寄り添い、家庭でできる関わり方を共に考えていく「ペアレント・トレーニング」の基礎も学べます。
【揺るぎない自信】
「これでいいのだろうか?」という手探りの関わりから、「根拠に基づいた支援」ができるようになります。この自信は、あなた自身の心の安定にもつながり、子どもとより穏やかに向き合えるようになります。
>>児童発達支援士の口コミや評判は?1万件超のアンケートから評価を徹底解析!
あなたの「力になりたい」を、確かな力に
「私には無理かもしれない…」
そう思う必要は全くありません。児童発達支援士の資格は、通信講座で学ぶことができ仕事や子育てをしながらでも、ご自身のペースで取得を目指せます。初めてこの分野の学習をするという方でも安心して受講できる構成となっています。
何より大切なのは、「子どもの可能性を信じ、その成長を支えたい」という、あなたのその温かい気持ちです。
【保護者の方なら…】
我が子にとって最高の理解者であり、最強のサポーターになることができます。日々の声かけや関わり方が変わり、子育てそのものが楽になるかもしれません。
【保育士や教員の方なら…】
クラスにいる気になる子への対応力が格段に上がり、職場での信頼も厚くなります。キャリアアップの大きな武器となるでしょう。
【子どもと関わる全ての方へ…】
あなたが身につけた知識とスキルは、一人の子どもの人生を、そしてその家族の未来を、明るく照らす希望の光となります。
【まとめ】発達障害の種類を徹底解説|子どもの特性を理解し、未来を支えるためにできること
発達障害は多様な特性の集まりであり、決して「欠点」ではありません。一人ひとりが持つユニークな個性です。しかし、その特性と環境がうまく噛み合わない時、子どもたちは大きな困難を感じ、自信を失ってしまいます。
私たちの役割はそのミスマッチを解消し、子どもたちが自分の特性を強みとして活かせるような環境を整えてあげることです。
そのためには、まず私たちが「知る」こと。そして、その知識を「支える力」に変えていくことが求められています。合言葉は「理解は支援の第一歩」です。
この記事があなたの発達障害への理解を深める一助となったなら幸いです。そしてもしあなたが「もっと深く学びたい」「支援の輪を広げたい」と感じたなら、ぜひ「児童発達支援士」という道を調べてみてください。
あなたの一歩が、未来を創ります。困難を抱える子どもたちと、その家族が笑顔で過ごせる社会を、共に築いていきましょう。
一覧に戻る